「デッドリフトとハーフデッドリフトってどこが違うの?」
「ハーフデッドリフトのやり方を知りたい」
「ハーフデッドリフトをしていて腰が痛いと感じた場合はどうすれば良い?」
あなたはこんな疑問を持っていませんか?
ある程度は筋トレの経験があるのに、デッドリフトができないと悩んでいる人もいるのではないでしょうか?
腰に不安があると、床からバーベルを持ちあげるのは心配になりますよね。
ハーフデッドリフトは台からバーベルを持ちあげられるため、腰への負担が少ないトレーニングです。
この記事では、かっこいい背中を手に入れたいあなたのために、以下の情報について解説します。
- デッドリフトとハーフデッドリフトの違い
- 鍛えられる筋肉や効果
- やり方やポイント
腰が痛いがデッドリフトに取り組みたい方は、ぜひご覧ください!
ハーフデッドリフトとデッドリフトの違い

デッドリフトは床に置いたバーベルを持ち上げるプル系の種目です。バランスや正しいフォームの習得が難しく、トレーナーの指導を受けることが望ましいでしょう。
主に背中の筋肉に効かせられ、大臀筋やハムストリングスも鍛えられます。
ハーフデッドリフトは台を使って少し高さのある状態からバーベルを持ち上げるため、姿勢を保ちやすい種目です。
デッドリフトができないと悩んでいる人は、ハーフデッドリフトから取り組むとよいでしょう。
ハーフデッドリフトは動作が小さく、鍛えられるのは背中の筋肉に限定されるものの、集中してトレーニングできるのが利点です。
デッドリフトより高重量のバーベルを扱えるので、中級者や上級者が背中の筋肉を強化したり、筋肥大させたりしたいときにも使えます。
ハーフデッドリフトで鍛えられる筋肉3つ

ハーフデッドリフトを行う場合には、肩甲骨の内転と肩関節の伸展の動きを意識します。
主に背中に効かせられ、鍛えられる筋肉は以下の3つです。
- 広背筋
- 僧帽筋
- 脊柱起立筋
それぞれ詳しく確認していきましょう。
1. 広背筋
広背筋は肩甲骨の下から腰にかけて広がっている筋肉です。肩関節と密接しているため、肩の動きにもかかわってきます。
以下のような動作で使われるので覚えておきましょう。
- 肩を回す
- 背筋を伸ばす
- 上半身をひねる
日常生活の中では、引く動作を行うときに使われています。
広背筋は体の中でも大きな筋肉のひとつなので、鍛えると基礎代謝の向上が期待できるでしょう。ただし意識して鍛えないと大きくなりません。
ハーフデッドリフトでは肩を引きながら持ちあげると広背筋に効いてきます。鍛えると姿勢の維持が楽になり、逆三角形の体型が目指せるでしょう。
2. 僧帽筋
僧帽筋は頭と首の境目から肩甲骨まで広がっている筋肉です。
上部・中部・下部の3つにわかれており、それぞれ関係する動作が違います。肩甲骨の安定や動作に影響のある筋肉です。
僧帽筋をバランス良く鍛えることで、広い肩幅や丸く美しい肩をつくれます。肩こりや猫背の改善にも繋がるでしょう。
ハーフデッドリフトでは持ちあげるときに胸を張り、肩を引くことで僧帽筋に効いてきます。
3. 脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん)
脊柱起立筋は背骨に沿っているインナーマッスルで、以下の3つにわかれています。
- 腸肋筋(ちょうろくきん)
- 最長筋(さいちょうきん)
- 棘筋(きょくきん)
背筋を伸ばしたり、姿勢を保ったりするために必要な筋肉です。鍛えて肥大化すると背中に縦のラインが浮かびあがります。
広背筋と合わせて鍛えると、たくましい後ろ姿を目指せるでしょう。
女性にもおすすめ!ハーフデッドリフトを行うことで得られる4つの効果

ここからは、ハーフデッドリフトを行うことで得られる効果を解説していきます。
- 上半身の強化
- 基礎代謝の向上
- 姿勢の改善
- 肩こり改善
男性だけでなく女性にも嬉しい効果がありますので、順番に紹介していきます。
1. 上半身の強化
ハーフデッドリフトは、背筋群を中心に鍛えるトレーニングですので、上半身の強化につながります。女性であれば、バストアップ効果も期待できます。
上半身を鍛えることで、相対的にウエストを細く見せる効果もあるので、筋肥大とダイエットのどちらが目的あっても取り入れたいトレーニングです。
2. 基礎代謝の向上
ハーフデッドリフトは基礎代謝向上にもつながります。
この種目で鍛えられる3つの筋肉(広背筋、僧帽筋、脊柱起立筋)は、体の中でも特に大きな部位です。これらを鍛えることで、体全体の筋肉量が増えるため基礎代謝も向上します。
ハーフデッドリフトにより基礎代謝が向上することで、結果的に太りにくい体質になります。
3. 姿勢の改善
姿勢の改善も、ハーフデッドリフトで得られる効果の一つです。
ハーフデッドリフトで鍛えられる僧帽筋と脊柱起立筋は、姿勢を維持する筋肉です。これらの筋肉を鍛えることで、正しい姿勢で支えられるようになります。
4. 肩こり改善
僧帽筋を鍛えることで、肩こり解消にもつながります。
僧帽筋は肩甲骨を寄せたり、下から腕を引き上げる動きを担っています。ハーフデッドリフトを行うことで、僧帽筋へ強い刺激を与えられるため、背中上部の厚みが増すだけでなく、肩こり解消につながるのです。
ハーフデッドリフトのやり方を4ステップで解説

ハーフデッドリフトはバーベルを上下させるだけの簡単な動作になります。
しかし、高重量を扱う強度の高いトレーニングのため、正しいフォームで取り組むことが大切です。やり方のポイントを以下4つのステップで解説します。
- バーベルの重さを設定する
- スタートの姿勢をとる
- バーベルを持ち上げる
- バーベルをおろす
それぞれ詳しく確認していきましょう。
1. バーベルの重さを設定する
バーベルの重さは体重の7~8割ほどに設定します。
例えば体重が70kgの場合は49kg~56kg程度です。筋トレの経験者で物足りない場合は、少しずつ重くします。
重量はあくまで目安のため、無理をしない重さで取り組みましょう。
最初のうちは負荷を高くするより、フォームを身につけることが大切です。軽めの重さでフォームを体に覚え込ませます。
8~12回程度、持ち上げられるくらいの重さに設定しましょう。適切な重さが分からない場合には、細かく調整しながらベストな重量を探してみてください。
筋肉の成長とともに、重さを少しずつ増やしていきましょう。
2. スタートの姿勢をとる
バーを膝の位置にセットして重りを取り付けます。以下のようにスタートの姿勢を取りましょう。
- 足は肩幅にひらく
- かがむ姿勢をとる
- 腕の力を抜いてまっすぐさげる
- 手幅は肩幅よりやや広めにバーベルをつかむ
バーベルを持つとき、腰が丸まらないように注意しましょう。
3. バーベルを持ち上げる
バーベルを持ち上げるとき、背中が丸くなると腰に強い負荷がかかります。
背中に力を入れた状態で、首から腰までまっすぐに保ちましょう。
- 膝はつま先と同じ角度にする
- 膝を伸ばしながらバーベルをゆっくり持ち上げる
- 持ちあげながら胸を張り、肩を後ろに引いて肩甲骨をよせる
- 太ももの高さまで持ちあげ、2~3秒キープする
持ちあげるときに膝を後ろに引き、腰を前にだすことを意識すると背中が丸まりにくいです。顎があがって首を伸ばさないように注意します。目線はまっすぐ前を向きましょう
4. バーベルをおろす
バーベルをおろすときも引き上げるときと同じく、背中はまっすぐに保ちます。以下のようにバーをおろしましょう。
- 腰と膝を折りながらバーベルをゆっくりおろす
- 腰を後ろに突き出すような姿勢を意識する
- 台に触れたら置かずにまた持ちあげる
休憩を挟みながら、8回~12回を1セットとし、3セットを目安に行います。筋肥大より体を引き締めたい人は、軽めの重量で15回~20回程度やりましょう。
バーベルを台に置くときは、上半身を起こすような姿勢で戻します。
ハーフデッドリフトが背中を鍛えるのにおすすめな4つの理由

次に、ハーフデッドリフトに取り組むメリットをわかりやすく解説します。
- 背中を集中的に鍛えられる
- 腰への負担を軽減できる
- 高重量を扱える
- バーベルの高さを変えられる
1. 背中を集中的に鍛えられる
デッドリフトは全身に効かせられる分、色々な筋肉を意識する必要があり、刺激が分散しやすいです。
一方でハーフデッドリフトは下半身の動きが少ない分、集中的に背中へ刺激を入れられます。ただし、腰のあたりに負荷が集中しないようにしましょう。
背中の下部だけ成長してしまうとバランスが悪くなってしまいます。腰を痛めるリスクもあるでしょう。
ハーフデッドリフトは、背中の筋肉を追い込みたい人に最適なトレーニングです。体に厚みがでて逆三角形の体型を目指せますよ。
2. 腰への負担を軽減できる
床からバーベルを持ち上げるデッドリフトは腰への負担が高いです。
腰に不安のある人は腰痛が悪化したり、痛めたりすることが考えられるため、おすすめできません。
ハーフデッドリフトのトレーニングは可動域が狭く、腰への負担は少ないのが特徴です。
軽い重量なら初心者にも取り組みやすいでしょう。
腰の筋肉が刺激されているように感じたら、腰に負荷がかかっている証拠です。フォームを見直し、腰を反らさないようにまっすぐキープしましょう。
かかと重心を意識すると腰に力が入りにくいです。
腰への負担を軽減するために、自分に適した重量で取り組みましょう。
3. 高重量を扱える
ハーフデッドリフトはデッドリフトよりも可動域が狭いため、高重量を扱えます。
デッドリフトよりも強い負荷を加えられるので、効率良く筋肥大が見込めるでしょう。
トレーニングを続けていくと、いつもの重さでは筋肉に効かない停滞期がやってきます。
フリーウェイトは床からバーベルを持ち上げるため、高重量は腰への負荷が大きいです。
ピンポイントで背中を追い込めるハーフデッドリフトは、成長が感じにくい停滞期に効果的でしょう。
4. バーベルの高さを変えられる
ハーフデッドリフトは台にバーベルをセットできるので、骨格・柔軟性・筋力に合わせて高さの調整が可能です。
デッドリフトはバーベルを床置きするため、どんな体型の人でも高さは重りの半径になります。背の高い人は深くかがむ必要があるでしょう。
ハーフデッドリフトなら、自分の体型に合わせてバーベルをセットできます。
ハーフデッドリフトでも疲れてくると、上半身をまっすぐ保てず腰が丸まってしまいます。
骨盤が後傾しない範囲で膝を曲げ、手を下げた位置にバーベルを設置しましょう。
自分に合った高さなら、フォームが崩れにくくケガのリスクは少なくなります。
ハーフデッドリフトを行っても意味ない?効果が出ないときに見直すべき4つのポイント

このコラムを読んでいる方の中には、ハーフデッドリフトを行っても効果が感じられず、これ以上続ける意味がないのではと考える方もいるのではないでしょうか。
効果が出ないと感じる時は、下記のポイントを見直していきましょう。
- 肩甲骨を寄せる
- 反動をつけない
- 動きの強弱をつける
- 休息を取りながら行う
これらのポイントを意識することにより、ハーフデッドリフトの効果を感じられるはずですよ。順番に見ていきましょう。
1. 肩甲骨を寄せる
肩甲骨を寄せて、胸を張るようにすると効果的です。
ハーフデッドリフトを行う際に、腰が曲がってしまうと余計な負荷がかかります。肩甲骨を引き寄せるイメージで行いましょう。
2. 反動をつけない
ハーフデッドリフトは重量があるバーベルで行うため、無意識に反動をつけてしまいがちです。
負荷をかけて行うトレーニングですので、反動をつけてしまうと効果も半減してしまいます。
また、反動をつけて行うと関節や靭帯に負荷がかかりますので、注意が必要です。
3. 動きの強弱をつける
強弱をつけて行うことで、ハーフデッドリフトの効果を高められます。
具体的には、下記をイメージします。
- バーベルを下ろす際はゆっくり
- バーベルを上げる際は早く
下ろす際は重さに耐える動きになるのでゆっくりと下ろします。上げる際は力を出力するタイミングなので、早く上げることにより、負荷をかけることが可能です。
4. 休息を取りながら行う
ハーフデッドリフトを行う際は、適度に休息をとりながら行いましょう。
無理して負荷をかけ続けると疲れによりフォームも乱れ、ケガにつながる恐れがあります。
ハーフデッドリフトを行える回数は人によって異なりますので、正しいフォームを維持できる限界が来たら、無理をせずに休息をとりましょう。
ハーフデッドリフトをやる際の注意点4つ

ハーフデッドリフトには利点もありますが、注意点もあります。気をつけたい点を4つにまとめました。
- トレーニングの最後にやる
- 気軽に取り組めない
- 下半身を強化できない
- 毎日やらない
ひとつずつ確認していきましょう。
1.トレーニングの最後にやる
高重量を扱うハーフデッドリフトは握力を使います。トレーニングのメニューを組む際は、最後に持ってくるとよいでしょう。
ハーフデッドリフトをトレーニングの最初に持ってくると、握力を使う他の種目で本来の力が発揮できません。
肩や背中の筋肉には余裕があるのに、手が痛くてトレーニングを中断することもあるでしょう。
パワーグリップを使うと、手にかかる負担が軽減でき、握力に余力を残せます。
パワーグリップは手のひらのベロ部分をバーに巻きつけて使うため、マメの防止にもなりますよ。
2. 気軽に取り組めない
ハーフデッドリフトでトレーニングするためには、高重量の重りや耐久製の高い床などの設備が必要になります。
音や衝撃が大きいので通常はジムで行うことが多いです。
ジムによっては設備がないところもあるので、ハーフデッドリフトでトレーニングが可能か入会前に確認しておきましょう。
気軽に取り組めない種目ですが、アイテムを揃えれば自宅でもトレーニングが可能です。
ジムに通わず自宅で行うなら、ジムより軽い重量のものを揃えましょう。
床材を傷めないように保護マットを敷いたり、重りの部分には厚めのクッションを敷いたり念入りな準備が必要です。
3. 下半身を強化できない
背中だけでなく下半身を強化したい目的があるなら、ハーフデッドリフトよりデッドリフトの方がよいでしょう。
床から引き上げるときに、太ももやお尻の筋肉が使われます。
ハーフデッドリフトは下半身の動きが少なく、鍛えられるのは背中がメインです。
デッドリフトの方が全身の筋肉を使ってトレーニングできるので、運動能力を向上させたい場合にも向いています。
4. 毎日やらない
負荷の高いハーフデッドリフトを毎日やるのは逆効果です。
広背筋は体の中でも大きい筋肉のため、回復には48時間~72時間ほどかかります。
トレーニングで傷ついた筋肉を休息させることで筋肥大に繋がります。
効率よく筋肉を成長させるには週2~3回にとどめ、休息日を挟みながら無理なく鍛えましょう。
下半身のトレーニングでも、脊柱起立筋を多用する種目はあります。
例えばスクワットは、ハーフデッドリフトの筋トレと連続させない方がよいでしょう。
背中と足をトレーニングする間に休息日を設けたり、背中を鍛えた翌日はスクワットを省いたり、スケジュールを工夫します。
ハーフデッドリフトで腰が痛いと感じる時はフォームを見直す
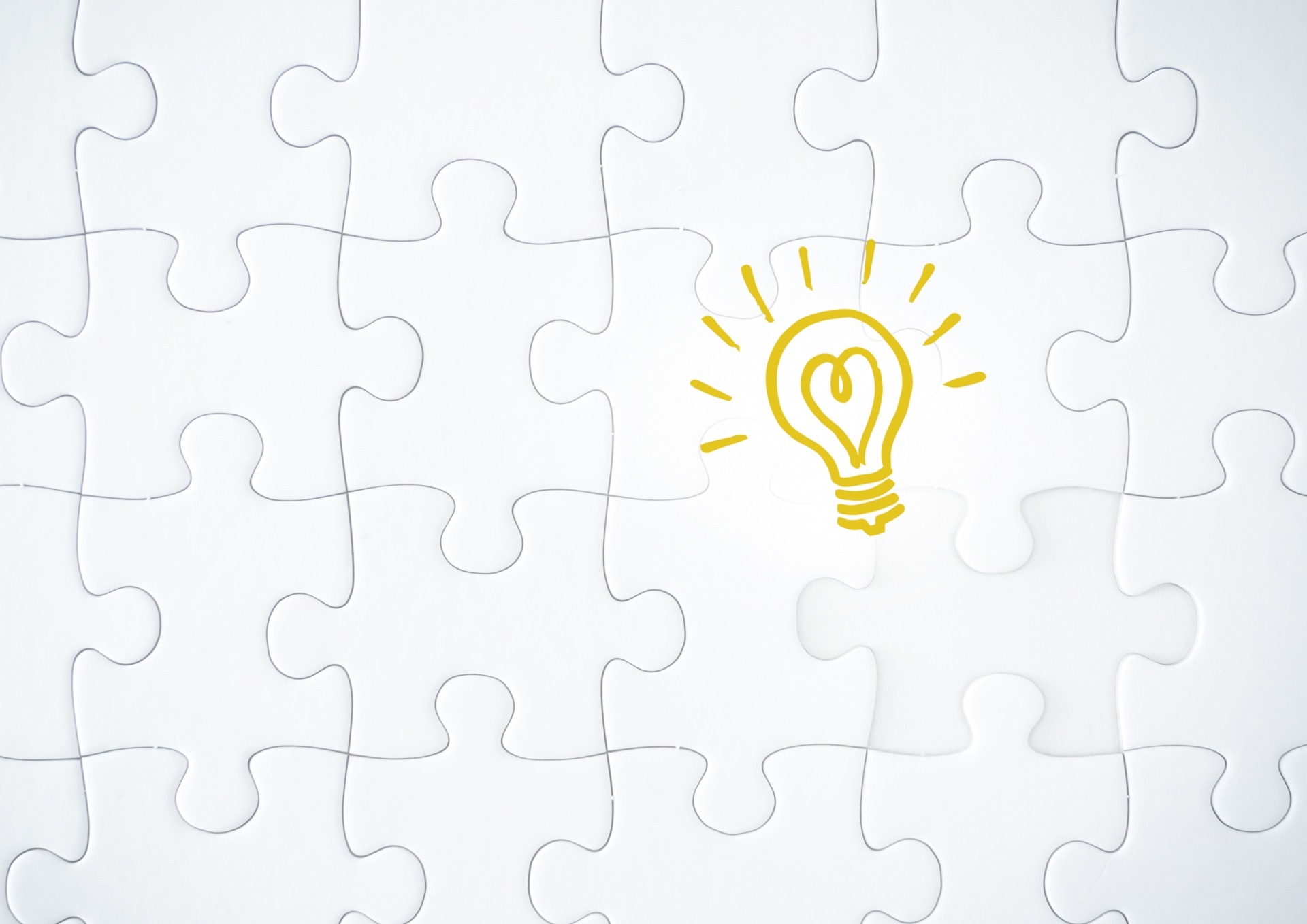
ハーフデッドリフトを行って腰が痛いと感じる時は、フォームの見直しを行いましょう。見直す際の主な注意点は下記です。
- 腰が丸まっていないか
- 腰を反りすぎていないか
- 重心がつま先に偏りすぎていないか
- バーベルが斜めになっていないか
また、フォームを見直すのはもちろん、トレーニング前はウォーミングアップやストレッチを必ず行いましょう。
ハーフデッドリフトは筋肉への負荷が大きいため、体をほぐさずに行うとケガにつながりやすくなります。
トレーニングを行って痛みを感じた時は、無理せず体を安静にしましょう。骨が痛む場合は、整形外科で診察を受けにいくことをおすすめします。
腰を痛めてしまうと、トレーニングだけでなく普段の生活にも影響が出てしまいます。
ハーフデッドリフトで引き締まった背中をつくる

ハーフデッドリフトは、筋トレ初心者から上級者までおすすめのトレーニングです。
フリーウェイトのデッドリフトより腰への負担が少なく、高重量のトレーニングにも取り組めます。
トレーニングを行っても効果がないと感じた時や、腰の痛みが出てきた時はフォームの見直しを行いましょう。
ハーフデッドリフトは集中して背中をトレーニングしたい人に最適です。
逆三角形の体型を目指して、ハーフデッドリフトで背中を引き締めましょう。
このコラムでは、他にもダイエット・ボディメイクに関するお役立ち情報を発信しています。ぜひ他の記事もご覧ください。
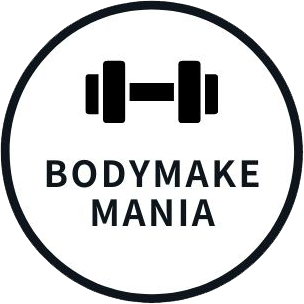














 トレーニング
トレーニング





