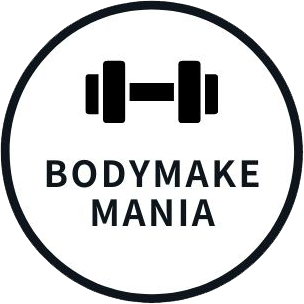「ダンベルで三角筋は鍛えられる?」
「どんなメニューを組んだらいい?おすすめを具体的に知りたい!」
あなたにはこんな疑問はありませんか?
三角筋を鍛えるトレーニングはたくさんありますが、それをどう取り入れたらいいのかわからない人は多いでしょう。
この記事では、ダンベルを使って三角筋を鍛えたいあなたに向けて、以下の情報について解説します。
- ダンベルで三角筋を鍛えるコツ
- おすすめの筋トレメニュー
- メニューの組み方と効率アップのポイント
最後まで読めば、力強い肩が手に入ること間違いなし。ぜひ参考にしてください!
ダンベルで鍛えるべき三角筋とは

三角筋は、肩を覆うようにして付いている筋肉です。
大きく前部、中部、後部に分かれており、キレイな肩周りを作るには、バランス良く鍛えることが大切です。
ただ、部位によって鍛えやすさは異なります。
前部はベンチプレス、ダンベルプレス等の大胸筋トレーニングで同時に鍛えられますし、中部も三角筋全体を鍛えれば十分です。
しかし、後部は負荷を与えにくく、目にも見えにくい部位のためしっかり意識すべきですね。トレーニング漏れがないよう、リアレイズ等を積極的に取り入れましょう。
ダンベルで三角筋を鍛える3つのコツ

ダンベルで広背筋を鍛える際は、以下の3点に注意しましょう。
- 鍛えたい部位を意識する
- 可動域を広げる
- 負荷のかかる感覚を身に付ける
それぞれ詳しく解説します。
(1)鍛えたい部位を意識する
1つ目のコツは、鍛えたい部位を意識すること。
前述の通り、三角筋は3つの小部位に分けられます。なんとなくトレーニングしているだけだと負荷が偏ってしまいますから、目的に応じてそれぞれを意識したメニューを組むことが大切です。
例えば、前方に丸みのある肩を作りたいなら前部、肩幅を広げたいなら中部、厚みを作りたいなら後部といった具合ですね。
どんな体になりたいのかによって、取り組むべきメニューは変わってきます。
(2)可動域を広げる
2つ目のコツは、可動域を広げること。
可動域とは、筋肉を動かす範囲のことです。三角筋に限らず、筋肉を大きく動かせば動かすほど効率的に負荷を与えられます。
例えばダンベルショルダープレスなら、腕がまっすぐになるまでダンベルを上げ、拳が肩と同じ高さになるまで下げること。これを意識するだけで、同じ重量でも与えられる負荷は段違いに変わりますよ。
(3)負荷のかかる感覚を身に付ける
3つ目のコツは、負荷のかかる感覚を身に付けること。
肩は上手く鍛えるのがやや難しい部位です。特に、レイズ系のトレーニングはフォームが崩れがちですから、まずは「どう動かせば負荷がかかるのか」を体で覚えてしまうと良いでしょう。
例えばリアレイズなら、一旦ダンベルを持たずに腕を後ろに引いてみて、三角筋後部に負荷がかかる角度、スピード、ひじの曲げ具合などを調整していきます。ダンベルを持つのは、それからでも遅くありません。
三角筋とその周辺を鍛えるダンベルトレーニング8選

当記事では、三角筋全体をバランス良く鍛えられるおすすめのトレーニングメニューを8つだけ厳選しました。
- ダンベルショルダープレス
- フロントレイズ
- サイドレイズ
- リーニングワンアームサイドレイズ
- ダンベルアップライトロウ
- リバースフライ
- リアレイズ
- ベントオーバーリアレイズ
部位ごとに紹介していますので、それぞれの手順とポイントを見ていきましょう。
(A)前部
1. ダンベルショルダープレス
ダンベルを肩の真上で持ち上げるトレーニングです。
三角筋全体を鍛えられますが、負荷はやや前部に偏ります。これをメインメニューとして行いながら、レイズ系で鍛えたい部位を狙い撃ちするのが肩トレの基本と言えるでしょう。
手順
- 椅子に深く座る
- 肩の上でダンベルを持つ
- ひじを伸ばしてダンベルを押し上げる
- ダンベルをゆっくりと下ろす
- 10回 × 3セット行う
効率を高めるポイント
- 可動域を広げる
- しっかり真上に持ち上げる
- 肩が上がらないようにする
2. フロントレイズ
体の前方へダンベルを上下させるトレーニングです。
先に解説した通り、前部はショルダープレスやベンチプレス等でも鍛えられますので、優先度はあまり高くありません。
しかし、前部をさらに追い込んで大きな肩を作りたいなら、ぜひ取り組みましょう。
手順
- 足を肩幅と同じくらいに開いて立つ
- 体の前でダンベルを持つ
- 腕を伸ばしてダンベルを肩の高さまで上げる
- ゆっくりと下ろしていく
- 10回 × 3セット行う
効率を高めるポイント
- ひじが下がらないようにする
- 負荷を高めるときは、ダンベルを上げたまま数秒静止する
(B)中部
3. サイドレイズ
体の側面へダンベルを上下させるトレーニングです。
肩幅の広さを重視する場合におすすめです。こちらも、ショルダープレス等と合わせて取り組みましょう。
手順
- 足を肩幅と同じくらいに開いて立つ
- ダンベルを両手で持つ
- 体の真横にダンベルを持ち上げる
- ダンベルをゆっくりと下ろす
- 10回 × 3セット行う
効率を高めるポイント
- しっかり肩の高さまで持ち上げる
- 肩が上がらないようにする
4. リーニングワンアームサイドレイズ
柱などを掴み、片腕で行うサイドレイズです。
腕や肩をトレーニングする際は、片腕ずつ行うと狙った部位をさらに鍛えやすくなります。その分時間がかかりますので、余裕のあるとき行うと良いですね。
手順
- 柱などを掴む
- もう片方の手でダンベルを持つ
- 上半身を斜め45度くらいに倒す
- 腕と床が水平になるまでダンベルを持ち上げる
- ダンベルをゆっくりと下ろす
- 10回 × 3セット行う
効率を高めるポイント
- 筋緊張を切らさない
- ダンベルはゆっくりと下げる
- ひじを少しだけ曲げる
5. ダンベルアップライトロウ
ダンベルを逆手で持ち上げるトレーニングです。
こちらも中部に負荷を与えられます。ただ、どちらかというと全体寄りのトレーニングですので、ショルダープレスと置き換える形で取り組んでみましょう。
手順
- 足を肩幅くらいに開いて立つ
- ダンベルを両手に持つ
- ひじを先行して、拳を真上に引き上げる
- 肩の高さまで上げたら、ゆっくりと下ろす
- 10回 × 3セット行う
効率を高めるポイント
- 肩甲骨を寄せないようにする
- 背筋を真っ直ぐにする
6. リバースフライ
体を前傾させてダンベルを上げ下げするトレーニングです。
三角筋中部を中心に、後部や僧帽筋も鍛えられます。重点的に鍛えるならフロントレイズ、僧帽筋にもついでに負荷を与えたいならリバースフライを選ぶと良いですね。
手順
- 足を肩幅くらいに開いて立つ
- ダンベルを両手で持つ
- お尻を後ろに突き出して中腰になる
- そのままダンベルを上に上げる
- ゆっくりと下ろしていく
- 10回 × 3セット行う
効率を高めるポイント
- 上半身が反らないようにする
- 肩甲骨をしっかり寄せる
(C)後部
7. リアレイズ
体の後方へダンベルを上下させるトレーニングです。
三角筋後部を鍛える定番メニューですね。ただし、難易度は他のトレーニングと比べて高いので、負荷がかかる感覚を体で覚えることが重要になります。
手順
- 足を肩幅と同じくらいに開いて立つ
- ダンベルを握る
- 上半身を45度くらいに曲げる
- ダンベルを体の後方に向かって持ち上げる
- ゆっくりとダンベルを下げる
- 10回 × 3セット行う
効率を高めるポイント
- 羽ばたくようなイメージで行う
- 腕は限界まで後ろに上げる
- 負荷を高めるときは、ダンベルを上げたまま数秒静止する
8. フェイスプル
前傾姿勢のままダンベルを引き上げるトレーニングです。
肩方向に引くため、リアレイズよりも難易度は低め。どうしても広背筋後部が上手く鍛えられないなら、こちらを試してみると良いでしょう。
手順
- 足を肩幅と同じくらいに開いて立つ
- ダンベルを握る
- 上半身を45度くらいに曲げる
- 肩に向かってダンベルを引く
- ゆっくりと元に戻す
- 10回 × 3セット行う
効率を高めるポイント
- 肩甲骨を寄せない
- 軽めの重量で行う
- ひじを先行して動かす
三角筋をバランス良く鍛えるメニューの組み方

ここまで、三角筋に効くメニューを紹介しました。
しかし、実際にどんなメニューを選べばいいかわからないと思いますので、目的別のおすすめメニューについて解説します。
【初心者向け】
ショルダープレス or ダンベルアップライトロウ+フェイスプル
ショルダープレスは幅広い部位に効果があります。
これをメインにしつつ、広背筋後部を鍛えるフェイスプルを取り入れてみました。
リアレイズでも良いですが、初心者向けということで負荷をかけやすいのはこちらです。
これをベースに、理想の体に合わせてメニューを変化させていきましょう。
【肩幅を広くしたい場合】
ダンベルアップライトロウ+サイドレイズ +リアレイズ
ダンベルアップライトロウは、効果範囲がやや中部寄り。それにサイドレイズで追い込むことで、より肩幅が大きくなります。リアレイズもしっかり組み込みましょう。
【分厚い肩を作りたい場合】
リバースフライ+リアレイズ+シュラッグ
リバースフライは僧帽筋にも効くのが特徴。ベンチプレス等を行っているなら、前部への負荷はそちらで十分です。最後に、僧帽筋に集中的に負荷を与えられるシュラッグで仕上げはバッチリですね。
三角筋をさらに効率良く鍛える3つのポイント

トレーニングの効率をさらに高めるには、以下の3点を必ず意識しましょう。
- 適切な頻度でトレーニングする
- 食事の栄養バランスを整える
- 睡眠時間をしっかり確保する
それぞれ詳しく解説します。
(1)適切な頻度でトレーニングする
1つ目のポイントは、適切な頻度でトレーニングすること。
筋肉には「超回復」という成長サイクルがあります。超回復とは、筋肉がトレーニングで傷ついた後、時間をかけて修復されて以前より強くなることです。
以下は超回復にかかる時間をまとめた表です。
| 部位 | 筋肉 | 回復にかかる時間 |
| お腹 | 腹筋 | 24時間 |
| お尻 | 大臀筋 | 48時間 |
| 肩 | 三角筋 | 48時間 |
| 僧帽筋 | 48時間 | |
| 腕 | 上腕二頭筋 | 48時間 |
| 上腕三頭筋 | 48時間 | |
| 胸 | 大胸筋 | 48時間 |
| 背中 | 広背筋 | 72時間 |
| 脊柱起立筋 | 72時間 | |
| 脚 | 大腿四頭筋 | 72時間 |
| ハムストリングス | 72時間 |
三角筋の超回復には48時間かかります。
よって、トレーニングの頻度は短くても2日おきが適切。無理に負荷を与えると逆効果になってしまいます。
(2)食事の栄養バランスを整える
2つ目のポイントは、栄養バランスを整えること。
筋肉の成長には、タンパク質やアミノ酸、ビタミン・ミネラルと、様々な栄養素が必要になります。トレーニングだけでなく、食事の栄養バランスを整えましょう。
大切なのはPFCバランスを意識すること。
PFCとは、三大栄養素(タンパク質、脂質、炭水化物)の割合で、最適なバランスは次のようになります。
- タンパク質:15%
- 脂質:25%
- 炭水化物:60%
具体的には、以下のような食品がおすすめです。
タンパク質
- 肉類
- 魚
- 卵
- 納豆
- 豆腐
脂質
- 低脂肪牛乳
- 低脂肪ヨーグルト
炭水化物
- ご飯
- パン
- パスタ
食事改善が難しいなら、プロテインを活用するのも手です。
(3)睡眠時間をしっかり確保する
3つ目のポイントは、睡眠時間を確保すること。
筋肉は、寝ている間に分泌される成長ホルモンの働きで合成・修復されるため、睡眠不足はトレーニングに悪影響を与えます。
それに、寝不足だと十分なパフォーマンスを発揮できません。
理想的な睡眠時間は7〜8時間ほどですが、現代人の生活では実際にこれだけ寝るのは難しいかもしれません。
せめて就寝前のスマホやパソコンは避け、睡眠の質を高めるように心がけましょう。
三角筋はストレッチも重要!おすすめのストレッチ2つ

三角筋を鍛える際は、ストレッチも重要です。
トレーニング後にストレッチを行うことで、血行促進されて栄養が行き渡り、筋肉の成長や回復も早くなります。
肩が痛いと日常生活では辛いため、働く社会人が筋トレをするなら必ずストレッチもセットで行いましょう。
今回は、2パターンの肩ストレッチを紹介します。
(1)腕を伸ばすストレッチ
ラジオ体操等でよく行われる一般的な肩ストレッチです。
座ったままの姿勢でできますので、デスクワークで肩が凝っている場合に最適だと言えるでしょう。
手順
- 右腕を左側にまっすぐ伸ばす
- 左腕で右ひじを押さえる
- そのまましっかり体に引きつける
- そのまま10〜20秒キープする
- 反対側も同じように行う
効率を高めるポイント
- 伸ばした腕はまっすぐにする
- 腕にあごが乗るくらい引きつける
(2)ひじを引っ張るストレッチ
バンザイの姿勢で行うストレッチです。
腕を思い切り持ち上げるため、単純なストレッチ効果だけでなく、リフレッシュ効果も得られます。
手順
- 両手を組んで頭の後ろに回す
- 右ひじを下げて、もう片方の手を引っ張る
- 限界まで下げたら、ゆっくりと元に戻る
- 反対側も同じように行う
効率を高めるポイント
- 手は指同士で軽く組む
- 手を引っ張るときに体を少しねじる
まとめ|ダンベルで三角筋を鍛える際は、前部・中部・後部をそれぞれ意識しよう!

三角筋を鍛える際は、前部、中部、後部に分かれており、どこに重きを置くかによってトレーニングで得られる結果も変わってきます。
最後に、ダンベルで肩を鍛える際のポイントをおさらいします。
- 鍛えたい部位を意識する
- 可動域を広げる
- 負荷のかかる感覚を身に付ける
正しい方法でトレーニングを継続し、惚れ惚れするような逆三角形の体を手に入れてください!
このコラムでは、他にもダイエット・ボディメイクに関するお役立ち情報を発信しています。
ぜひ他の記事もご覧下さい。