「懸垂は肩こりの改善になる?」
「懸垂が肩こりに効くと言われているのはなぜ?四十肩が心配だから予防したい」
あなたはこんな疑問を持っていませんか?
仕事がデスクワークばかりだと、肩こりが気になりますよね。年齢的に四十肩が心配な人もいるのではないでしょうか。
懸垂は背中や肩周りなど、幅広い筋肉を鍛えられる筋トレです。継続すれば筋肉量が増え、肩こりが改善に向かうでしょう。
こちらの記事では、肩こりに悩むあなたのために、以下の方法について解説します。
- 肩こりに効く懸垂のやり方
- 懸垂で鍛えられる部位
- 取り組むときの注意点
懸垂の正しいやり方を身に付けて肩こりに悩まされる日々から解放されますので、ぜひ最後までご覧ください!
懸垂が肩こりに効く3つの理由

懸垂が肩こりに効く理由としては、以下の3つが挙げられます。
- 血行不良を改善できる
- 肩甲骨はがしの効果がある
- 姿勢が正しくなる
懸垂と肩こりの関係性を理解していくためにも、1つずつチェックしていきましょう。
1. 血行不良を改善できる
肩にある僧帽筋は、肩甲骨を動かしたり安定させたりするために必要な筋肉です。
そこで、僧帽筋の強ばりや緊張、血行不良が起こってしまうと、肩こりや四十肩の原因になります。
四十肩は肩の関節が炎症を起こす症状で、腕が上がらなくなる人もいるでしょう。
筋肉が強ばる原因は、長時間のデスクワークやスマートフォンの利用など、現代の生活習慣が影響しています。同じ姿勢をとり続けると筋肉は小さく硬くなり、血行不良を引き起こすのです。
懸垂を行うと背中や肩周りの筋肉がほぐれます。ストレッチ効果で血行が促進され、肩こりの症状が和らいでいくでしょう。僧帽筋を鍛えて筋力をアップさせれば、肩こりや四十肩の予防になりますので、懸垂を継続させて肩の血行不良を改善していきましょう。
2. 肩甲骨はがしの効果がある
懸垂を行うことで、肩甲骨はがしの効果が期待できます。
肩甲骨はがしとは、凝り固まった肩甲骨周辺の筋肉とファシアの緊張をほぐすことを指します。ファシアは皮膚、筋肉、臓器、血管、骨を覆っている組織です。
懸垂を行うことで、肩甲骨まわりの筋肉、ファシアにストレッチ効果を与えて、肩こりを防げます。
3. 姿勢が正しくなる
猫背を放っておくと、前のめりになる関係で背中が丸まり、首の筋肉が硬直して血行が悪くなります。その結果、肩こりに繋がりやすくなってしまうでしょう。
そこで、懸垂を行うことで、上半身の筋肉を集中的に鍛えられるため、姿勢を矯正して肩こりの改善が期待できます。
姿勢が悪いという自覚がある場合は、継続して懸垂を行い、肩こりを防ぎましょう。
懸垂で鍛えられる4つの部位

懸垂を行うことで、以下の4つの部位を鍛えられます。
- 広背筋
- 菱形筋(りょうけいきん)
- 上腕二頭筋
- 大円筋
それぞれの部位の詳細も含めて、確認していきましょう。
1. 広背筋
広背筋は背中にある筋肉で、肩甲骨の下から背筋に沿って伸びています。背中にある筋肉の中でも最も大きいのが特徴です。
広背筋は主にものを引き寄せたり、荷物を持ったりする際に使われる筋肉ですが、頻繁に使われるわけではありません。そのため、広背筋を鍛える場合は、存在を意識してトレーニングを行わないと発達しません。
懸垂は高負荷なトレーニングなので、継続して行うことで効率よく広背筋を鍛えられるでしょう。
こちらの記事では、広背筋について詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
2. 菱形筋(りょうけいきん)
菱形筋は、背骨と肩甲骨にあり、僧帽筋や広背筋をサポートする筋肉です。
懸垂には菱形筋を引き延ばす効果があるので、継続して行うことで発達が期待できます。
肩甲骨の動きが安定しやすくなるので、鍛えるメリットが大きい部位と言えるでしょう。
3. 上腕二頭筋
懸垂を行うことで、上腕二頭筋に大きな負荷を与えられるので、発達が期待できます。
上腕二頭筋は腕の上部に位置しており、いわゆる力こぶにあたる筋肉。鍛えることでより腕が太くなるので、たくましい印象を周りに与えられます。
上腕二頭筋を鍛えておくと、重いものを運ぶ際にも楽になるので、鍛えておくメリットは大きいと言えるでしょう。
4. 大円筋
大円筋は、肩甲骨の下あたりに存在する小さめの筋肉です。広背筋をサポートするため、よりスムーズな動作が期待できるでしょう。
他にも、大円筋を鍛えることで「きれいな逆三角形が作れる」「背中の立体感が出せる」というメリットがあります。
たくましい上半身を作りたいという方は、懸垂を続けて大円筋を鍛えていきましょう。
懸垂の正しいやり方

懸垂を正しく行って効率よく筋肉を鍛えるためにも、以下の正しいやり方を把握しておきましょう。
- 自分側に手のひらを向ける
- バーをしっかりと握る
- 手幅は肩幅と同じくらいに開く
- 肩甲骨を寄せていく
- 顎がバーと同じ高さになるまで体を持ち上げていく
- 持ち上げた状態を2~3秒くらいキープ
- 肘を伸ばしきらないように元に戻す
- 10回 × 3セットで繰り返す
ケガのリスクを抑えるためにも、早い段階で正しいやり方をマスターしておきましょう。
こちらの記事では、懸垂の正しいやり方について詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
肩こりに効く懸垂のやり方3つ

肩こりを解消するため、懸垂は正しいやり方で実施しましょう。以下の3つにまとめました。
- 正しいフォームで実施する
- 肩幅より広くバーを掴む
- ゆっくり実施する
ひとつずつ確認していきましょう。
1. 正しいフォームで実施する
肩こり対策なら、広背筋や僧帽筋に効かせるやり方が効果的です。
正しいフォームで取り組むことで、しっかりと背中の筋肉に刺激が入り、肩こりの改善が期待できます。
正しいやり方は以下のとおりです。
- 肩幅と同じかやや広めにバーを握る
- 肩甲骨を背筋中央に引き寄せて胸をバーに近づける
- 顎とバーが同じ高さになるまで体を持ち上げる
- ゆっくり体を下げて元の姿勢に戻る
10回ほど同じ動作を繰り返し、休憩を30秒~1分挟みながら3セット実施します。
呼吸を止めないように気をつけ、体を持ち上げるときに息を吐き、下ろすときに息を吸いましょう。
フォームが崩れると、広背筋や僧帽筋に刺激が入りません。
回数をこなすより、正しいフォームで行うことを意識します。最初のうちは10回より少ない回数でも問題ありません。
2. 肩幅より広くバーを掴む
バーを掴む位置が肩幅より狭いと、広背筋や僧帽筋ではなく、腕の筋肉が使われます。
肩幅より広い位置でバーを握るようにしましょう。
通常であれば肩幅よりやや広めにバーを掴みます。懸垂に慣れてきたら、肩幅の2倍ほど手を広げて行うワイドチンニングに挑戦するのも良いでしょう。
肩をすくめると広背筋への負担が小さくなります。胸を張り、背中の筋肉を意識して肩甲骨を寄せるように取り組みましょう。
3. ゆっくり実施する
懸垂はゆっくり行った方が筋肉に刺激が入りやすいため、焦らず行いましょう。正しいフォームを意識してゆっくり体を持ち上げ、下ろす動作もゆっくりと行うことで、筋肉を痛めにくくなります。
初心者の場合は筋力が弱く、肩こりで筋肉が硬くなっていることが多いです。筋肉が強ばったまま急に懸垂をし始めると、肩を痛めてしまいます。今まで懸垂をやったことがない人は、急に始めないようにしましょう。
懸垂は自分の全体重を引き上げる負荷の高い自重トレーニングです。懸垂で肩が痛くなってしまった人は、肩への負荷が高すぎたと考えられます。まずはダンベルなどで、ある程度の筋力をつけてから懸垂を始めましょう。
数回からスタートし、勢いよくジャンプしてバーを掴むなど、過剰な反動はつけないことが大切です。筋肉へのストレッチ効果を感じながらゆっくり行いましょう。
懸垂をやるときの5つの注意点

懸垂の効果を高める際に注意すべきポイントを以下の5つにまとめました。
- 準備運動をする
- 顎を引く
- 適度な回数を守る
- トレーニングの間隔を空ける
- 首が痛い時の治し方を理解しておく
ひとつずつ確認していきましょう。
1. 準備運動をする
準備運動をしないで懸垂を始めると、首や肩を痛めることがあります。
トレーニングの前にストレッチを念入りに行いましょう。首や肩周りの筋肉を伸ばしておくと、ケガのリスクが軽減します。
肩周りのストレッチは、以下の方法が効果的です。
- 肩まわし
- チャイルドロック体操
- スイマー体操
チャイルドロック体操は、正座の状態からお祈りのようなポーズで、上半身を前に伸ばすストレッチです。
スイマー体操は、うつ伏せの状態から頭上に手を伸ばします。気持ちよく肩がほぐれるので、試してみてください。
また肩と一緒に、首や肩甲骨のストレッチも合わせて行いましょう。
2. 顎を引く
懸垂で体を引き上げるときは、顎を上げずにしっかりと引きましょう。顎を引かないと首に負担がかかってしまいます。
首を痛めると寝違えたような痛みが続き、トレーニングができなくなったり、生活に支障をきたしたりするでしょう。
初心者のうちは筋力が弱く、腕の力でバーに無理矢理近づこうと顎をあげる傾向にあります。
顎を引いて視線を前方に向け、頭は固定した状態で懸垂を行いましょう。
3. 適度な回数を守る
懸垂は無理に回数を重ねると、首や肩を痛めるリスクが高まります。トレーニングが長すぎると、筋肉への刺激も少なくなってしまうのです。
10回を1セットにし、30秒~1分の休憩を入れて、3セット程度行いましょう。
初心者のうちは5回~6回でも効果はあります。慣れてきたら12回程度まで回数を増やしても良いでしょう。
ただし、回数は増やしすぎず、負荷が足りない場合は足に重りをつけて行います。
適度な回数の中で十分な負荷を感じられるよう、トレーニングに取り組みましょう。
4. トレーニングの間隔を空ける
懸垂は負荷の高いトレーニングのため、毎日行わないようにしましょう。週2〜3日程度の頻度が最適です。
筋肉が疲労から回復するためには時間が必要です。
傷ついた筋肉は、休息することで大きく成長します。この仕組みを「超回復」と呼び、計画的に繰り返すことで筋肉が強くなるのです。
筋肉痛が残っているうちは、筋肉の回復が間に合っていない状態なので、トレーニングを控えましょう。
広背筋や僧帽筋のような大きな筋肉は、回復するのに2~3日かかります。
トレーニングのスケジュールを決めて、筋肉をしっかり休ませることが大切です。
5. 首が痛い時の治し方を理解しておく
懸垂をやっていて、首が痛いと感じ始めたのであれば、まずは安静にしましょう。
筋肉が傷ついている可能性が高いので、修復する時間を与えることが大切です。
痛みが和らいできたら、以下の方法で血流を改善しましょう。
- 患部を温める
- ストレッチを行う
- マッサージを行う
痛みが残っている段階で懸垂を続けてしまうと、ケガに繋がりかねないのでしっかりと休みましょう。
懸垂が上手くできないときの対処法

懸垂は筋力が必要になるトレーニングなので、筋力不足だと上手くできないことがあります。
そこで、懸垂を上手くできるようになりたいのであれば、以下の方法で対策しましょう。
- 上半身を鍛える
- 腕の筋肉を鍛える
- 少しずつ回数を増やす
また、しっかりと休息をとってから懸垂を行うことも大切です。痛みが残っている中で懸垂しても長続きしないので注意しましょう。
肩や背中に効果のある懸垂3選

懸垂には様々な種類があり、腕や腹筋に効くトレーニングもあります。
肩こりを改善させるためには、肩や背中に効果のある懸垂を選びましょう。こちらでは3つの懸垂をご紹介します。
- 斜め懸垂
- プルアップ
- ワイドグリップチンニング
ぜひトレーニングの参考にしてみてください。
1. 斜め懸垂
斜め懸垂はバーの高さを低くし、足を床につけて行うので負荷は小さくなります。
懸垂でうまく体が上がらない人は、斜め懸垂から行うと良いでしょう。
- バーの高さをおへその辺りまで下げる
- 肩幅よりやや広めに順手でバーを握る
- しゃがんだ姿勢から足を前にずらす
- ひじを伸ばし、床にかかとをつけて体を斜めに伸ばす
- 体は一直線になるように保つ
- バーに胸をひきつける
10回を1セットとし、30秒の休憩を挟みながら3セット程度行います。体を一直線に伸ばしたときの角度が、床から45度以下になるようバーを調整しましょう。
2. プルアップ
プルアップは順手で行う懸垂です。広背筋の上部や僧帽筋に効くトレーニングで、逆手より難易度があがります。
逆三角形の体を作るために必要な筋肉が鍛えられますよ。
- 肩幅よりやや広めに順手でバーを握る
- 顎がバーと同じ高さになるまで体を持ち上げる
- 上がりきったところで2秒キープ
- ゆっくりと体を下ろす
10回を1セットとし、30秒~1分間の休憩を挟みながら3セット程度行いましょう。
体を上げるときは上腕三頭筋、下げるときは上腕二頭筋を意識します。背中が丸まってしまうと、広背筋や僧帽筋に刺激が入らなくなるので注意しましょう。
3. ワイドグリップチンニング
通常の懸垂よりもバーを掴む手幅を広げることで、広背筋や僧帽筋を含む上半身の幅広い筋肉が鍛えられます。
肩こりの解消はもちろん、継続すれば背中が引き締まり、後ろ姿が美しくなるでしょう。
- 肩幅の2倍ほど手幅を取り、バーを順手か逆手で握る
- 足を軽く持ち上げる
- 肩甲骨を中央に寄せながら、バーを胸に近づける
- 上がりきったところで2秒キープする
- ゆっくりと体を下ろす
10回を1セットとし、30秒~1分間の休憩を挟みながら3セット程度行いましょう。目線は前方を向き、顎を引いて取り組みます。
自宅で懸垂する時に揃えたい3つの器具

懸垂は、ジムや公園の鉄棒などで気軽に行えるトレーニングです。
しかし、ジムに通えなかったり、公園で行うことに抵抗がある人もいるでしょう。
自宅でトレーニングするためには、器具を揃える必要があります。揃えたいアイテムは以下の3つです。
- 懸垂バー
- チンニングスタンド
- トレーニングギア
ひとつずつ確認していきましょう。
1. 懸垂バー
懸垂バーは、2,000円台から購入できる手軽なトレーニング器具です。
ジムに通う時間のない人やコストがかけられない人は、懸垂バーを活用しましょう。ジムに行けない日のトレーニング用に購入するのもおすすめです。
突っ張り棒タイプの懸垂バーなら、自宅のドア枠に取り付けて使えます。
ドア枠の傷が気になる人は、ドアに引っかけて使うタイプを検討しましょう。
懸垂バーは100kgまで耐えられるものもあるので、自重に合わせて選んでください。幅が伸縮するので、取り付けたい場所のサイズに合わせられます。
安全ストッパーがついたものを選べば、トレーニング中に懸垂バーが外れてケガをする心配はありません。
「初心者だからジムで懸垂するのが恥ずかしい」と考えている人は、まず懸垂バーを使って自宅で練習してみるのも良いでしょう。
2. チンニングスタンド
チンニングスタンドは、10,000円前後で購入が可能です。
部屋に設置するスタンド型のため、懸垂バーより場所が必要になります。自宅のスペースを考慮して選びましょう。
購入するときは、耐荷重量に注意します。安全にトレーニングを行うために、自分の体重より耐荷重量が重いものを選択しましょう。
慣れていないと反動をつけて懸垂してしまうことが多く、チンニングスタンドに体重以上の負荷がかかります。設置する床が安定していることも大切です。
チンニングスタンドは、斜め懸垂ハンドルがついた初心者用のモデルや、腹筋用のベンチを装備したマルチ懸垂マシンなど種類が豊富です。
懸垂以外のトレーニングを視野に入れて選ぶのも良いでしょう。
3. トレーニングギア
トレーニングギアは懸垂でマメができたり、手が痛くなったりするのを防いでくれます。
ジムや公園で懸垂に取り組むときにも便利なので、購入を検討してみてください。懸垂に適したトレーニングギアは、主に以下の2つです。
- パワーグリップ
- トレーニンググローブ
滑り止め効果があり、手のひらに汗をかいてもバーから手が離れにくいです。
手や腕に余計な力が入らないので、背中や肩に意識を集中できるでしょう。
パワーグリップはバーに巻きつけるベロが手のひら側についており、トレーニングによって着脱が必要です。
手に巻くだけの簡単な仕様で、グローブに比べて取り外しやすいでしょう。
グローブは、着けたまま懸垂以外のトレーニングができます。ただ、懸垂によるマメはパワーグリップの方ができにくいです。
こちらの記事では、自宅で懸垂する時に使える器具について詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
まとめ:懸垂で肩周りの筋肉を鍛えて肩こりを予防!まずは正しいやり方を覚えよう

肩こりや四十肩は、筋肉の衰えや血行不良が原因です。現代の生活スタイルでは、避けられない症状と言えるでしょう。
懸垂で肩まわりの筋肉を鍛えることで、予防や改善が期待できます。
正しいフォームと適度な回数を守りながら、取り組むことが大切です。
日本人は欧米人に比べると骨格や筋肉が華奢で、肩がこりやすい傾向にあります。
さらに40代以降になると筋肉が衰えて、肩こりを悪化させる人が増えるのです。
四十肩は肩こりの積み重ねによるもの。肩周りの筋肉を鍛えれば肩こりや四十肩を予防できるので、症状がひどくなる前に懸垂で肩まわりの筋肉を強化しましょう。
このコラムでは、他にもダイエット・ボディメイクに関するお役立ち情報を発信しています。ぜひ他の記事もご覧下さい。
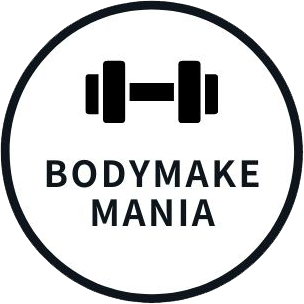













 トレーニング
トレーニング





